6月15日〜19日は技術補完訓練として、コミュニティ開発研修があった。
「そもそもコミュニティ開発研修ってなに?」って人も多いと思うけど、青年海外協力隊に応募するときは、120以上ある(らしい)職種から選んで応募する。
具体的には看護師だったり、自動車整備士だったり、教員だったり資格が必要なものがほとんど。ただコミュニティ開発に関しては資格が必要なくても参加できる。そしてそんな人たちに、「現地に行く前にワークショップの手法などを勉強しましょう」というのがコミュニティ開発研修。
内容はざっくり言うとPCM,PRA/PLAとかいうワークショップの手法を学んだり、協力隊としてのマインドを学んだり。
実際にやったワークショップの一例がこれ↓
(もしこれから研修に参加する人がいたら、読まないほうがいいかも。研修で内容を知った方が楽しいと思うから。)
ある隊員の体験:悲願のため池拡張工事
幹線道路をそれ、でこぼこ道を10kmも進むとZ村に到着する。首都から日帰りできるこの辺りは、ドナーたちがプロジェクトを競い合っているような、援助の多い地域。ダイスケはローカルNGOのコミュニティ開発担当として、Z村に住む唯一の開発ワーカーとなった。
早速、村に人々は水の整備をしてほしいと口々に訴える。Z村には水道も井戸もなく、雨水を溜めた池だけが水源。200人が生活用水として使うため、乾季に入ると水はみるみる減り、濁ってくる。村に住んで3ヶ月。飲み水の確保に苦労し、ダイスケ自身も水がこの村の一番の問題だと実感した。何回目かの住民全体会議において、村の有志で「水対策委員会」を発足させ、調査を始めた。行政、建設業者、保健所などに相談し、近くに水源はなく、井戸を掘るか溜池を拡張するしかないこと、住血吸虫※がいる地域なので溜池の水は危ないこと、井戸を掘るのには多額の費用がかかることなどがわかった。
「で、ダイスケは何してくれるの?乾季のうちに工事しないと雨が降り出すとできなくなるよ」と村人。「計画立てて、実行して行くのはみんな。皆んなは何をしたいんだい?俺は皆んながしたいことの手伝いをするよ。」と言ってみるが、村の人たちはピンとこない様子。それもそのはず、これまでZ村にやってきた開発ワーカーは皆、強烈なリーダーシップで「幼稚園を作ろう!」「植林しよう!」と村人を先導してきたのに、ダイスケは何も言い出さない。委員会は何度か話し合い、しばらくして「溜池拡張工事計画」を作り上げた。乾季中になんとか着工したいという。溜池はとうとう干上がり、村人は池の底に穴を掘り、染み出た茶色い水を汲んでいた。
住血吸虫がいるのに溜池拡張?!と驚いたが、村人自身でプロジェクトを作ったことと、工事への意気込みがダイスケには嬉しかった。それまでの村人はプロジェクトはドナーがやるもの、と他人任せだったから。
配属先のNGOと相談した結果、村人の意見を尊重し「溜池拡張工事」を採用したダイスケは、委員会の計画書に基づいて行くつかのドナーに資金援助を仰いだ。結果的にJICAからブルドーザーの借上料と建築資材の費用分を支援してもらえることになった。
早速、村人もダイスケも協力して連日作業し、工場は順調に進んだ。池に下りるための階段は村人総出で作った。みんなヘトヘトになりながら、無事に工事は終了!初めてみんなで一つのことを成し得た達成感と充実感に、ダイスケも村人も浸っていた。後は雨が降るのを待つだけ。ダイスケが「工事の完成パーティーはどうする?」と委員会に呼びかけると、「もちろんやろう!」の返事。
「じゃあ招待客は、まずはスポンサーのJICAだろ、それから…」
「なんでJICAを招待するの?」
「え?」
「招待されるのは我々でしょう、これはJICAのプロジェクトなんだから。」
「そうよ、そもそもなんで私たちがパーティーを開くの?JICAが『工事が完成しました』ってパーティーを開いて私たちを招待すべきでしょ?」
「働いたのは俺たちなんだぜ?」
「え??だってこれはみんなが欲しいって言った溜池で、みんなで工事するって決めたんじゃないか。それをJICAが支援してくれたんだよ。
「そうだけど、それはダイスケがもっと気前のいいスポンサーを見つけてこれなかったからだよ。ダイスケのせいで俺たちは足らない分を働かされたんだ。」
「溜池拡張工事をやるって決めて、工事計画を作ったのはみんなだろう?」
「そりゃそうさ。ダイスケは井戸を掘る多額の費用を用意できなかっただろう?溜池の工事費だって全額用意できないんだから。井戸にするか、それだってダイスケには決められなかったじゃないか。」
「これはみんなの村の問題だから、みんなで話し合って決めて欲しかったんだよ、俺は。」
「こうやって責任を押し付けるためかい?」
「……」
※血液中に寄生する吸虫。ヒトが河、湖、沼などの淡水に入って感染し、被害を与える。
これは実際にある隊員がガーナで経験した話であり、とてもリアルな感じ。
まだ活動期間が1年半残っている状況で、パーティーを開催せずに村民との仲を悪くするわけにもいかないし。村民がパーティーを折半で負担するとも考えにくい。うーん難しい…
ワークショップでは村民側と隊員側に分かれ、パーティーをどうするのか話し合うという内容。自分は村民側だったので、村民負担を断固拒否してた。笑
今回研修に参加して一番感じたことは、自分の意見を言う人が多いのかなーという印象。
自分は会社でワークショップなんてやらなかったから、比較対象が就活のグループワークになっちゃうけど、その時はおとなしい人が多かった印象。自分は割と他人を気にせず意見を言うタイプだからほとんど自分の意見が通って、割と拍子抜けというか、本当にみんなこの意見に賛成なのかなーと思う時も多々あった。
ただ今回は僕の意見に反論とかもあって、議論の進行スピードとしては遅くなるんだけど、自分としてはこっちの方がしっくりきた。
忌引きの関係で全日程は参加できず、話せなかった人も多いから、もっといろんな人と話したいなーと思う研修でした。

座学の風景。ワークショップは撮り忘れた。

日光白根山行ってきたけど霧で何も見えず…
ぜひリベンジしたい。
↓ランキング参加してます。
他の青年海外協力隊の人のブログも見れるのでぜひ。
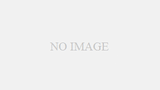

コメント